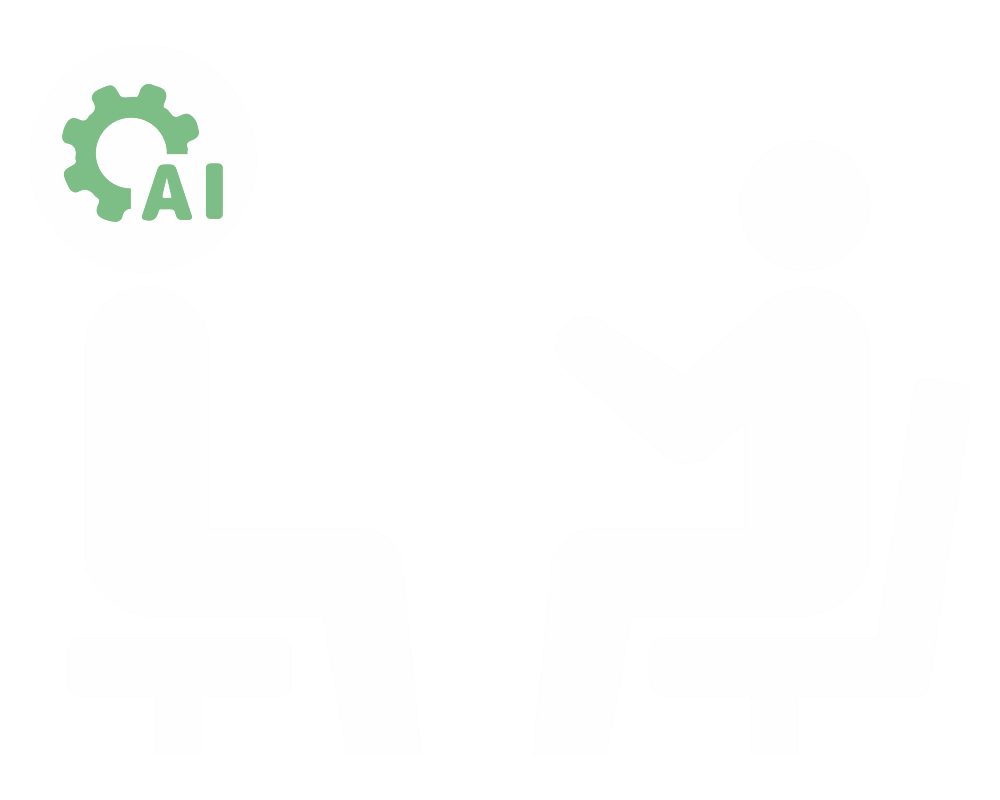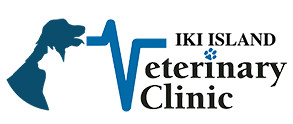-
 犬の病気
犬の病気
外耳炎/外耳道炎
外耳炎は犬や猫の外耳の表面に炎症が起こる病気で、垂れた耳のペットで一般的です。原因は異物、細菌、真菌、アレルギー、寄生虫などがあり、症状には耳のかゆみ、痛み、発赤、腫れ、悪臭、耳垢の増加が含まれます。治療は原因により点耳薬や内服薬、外科手術などが必要で、耳の清潔保持と適切なケアが予防に重要です。自己判断で治療を中断せず、獣医師の指示に従うべきです。 -
 犬の病気
犬の病気
甲状腺機能亢進症:Hyperthyroidism
甲状腺機能亢進症(こうじょうせんきのうこうしんしょう)は、特に猫で多く見られる病気です。のど元の気管の左右に張り付くように存在する豆粒ほどの小さな臓器(内分泌腺)である甲状腺から、体の代謝を活発にする役割をもつ甲状腺ホルモンが分泌されますが、そのホルモンの分泌が異常に増加することで起こります。 中~高年齢の猫がなりやすい病気(7歳以上の猫の10%以上がこの病気にかかっているという報告もあります。)で、毛艶が悪くなり、毛がバサバサしたり、活動性が増したり、落ち着きがなくなったり、食欲が旺盛なのに体重が減っていくというような症状が見られた場合は、甲状腺機能亢進症を疑います。猫種では雑種猫に多く、バーミーズ, トンキニーズ, ペルシャ, アビシニアン,ブリティッシュショートヘアーは罹率が少ないと報告[3]されています。 ちなみに犬で甲状腺機能亢進症が起こることは稀で、逆に甲状腺機能低下症が多く起こります。犬で起こりやすい犬種は、ゴールデン・レトリバー、シベリアン・ハスキー、ビーグル、ボクサーで、10歳以上の高齢犬が多いとされています。 -
 犬の病気
犬の病気
甲状腺機能低下症:Hypothyroidism
甲状腺機能低下症は犬の疾患で、主に高齢の大型犬で見られます。甲状腺からのホルモン不足により代謝が低下し、さまざまな症状が現れます。一般的な症状には体重増加、皮膚の問題、倦怠感、食欲の変化などが含まれます。診断には血液検査が必要で、治療には甲状腺ホルモン製剤の投与が行われます。早期発見と適切な治療が重要であり、予防法は特にありません。継続的な検査と治療が必要で、予後は一般的に良好です。 -
 犬の病気
犬の病気
会陰ヘルニア:Perineal Hernia
会陰ヘルニアは、犬の肛門周辺の筋肉間に隙間ができ、腹部臓器が出る病気で、未去勢の雄犬に多く見られます。腸や膀胱の出現により、排便や排尿の問題が生じます。診断には検査が必要で、外科手術が一般的な治療法です。去勢手術が再発予防に役立つことが知られており、過度な吠えなど腹部圧力の上昇を抑える訓練が予防に役立ちます。症状があれば早めの獣医師の診察が重要です。 -
 犬の病気
犬の病気
犬回虫症
犬回虫症は、寄生虫である犬回虫によって引き起こされる感染症で、主に犬が感染源です。感染は犬の糞便中の虫卵から起こり、感染すると消化器症状や体重減少などの症状が現れます。感染は犬仔犬への母子感染もあります。診断には糞便検査が行われ、治療には駆虫薬の投与が含まれます。予防には幼犬の駆虫と衛生的な慣行が重要で、人間にも感染する可能性があることに注意が必要です。 -
 犬の病気
犬の病気
レプトスピラ症
レプトスピラ症は、犬と人に感染する感染症で、レプトスピラ菌により引き起こされます。感染源は野ネズミなどの動物で、感染は感染動物の尿や汚染された水から起こり、経皮感染が主な経路です。症状は不顕性型、出血型、黄疸型に分かれ、いくつかは重篤で致命的です。ワクチン接種が予防策で、疑いがある場合は抗生物質の投与が行われます。感染リスクのある環境での注意が必要で、ズーノーシスとして知られています。 -
 犬の病気
犬の病気
犬コロナウイルス感染症(CCV)
犬コロナウイルス感染症(CCV)は、犬のウイルス感染症で、主に下痢や嘔吐などの消化器症状を引き起こす。特に仔犬は重篤な胃腸炎を起こし、犬パルボウイルスとの混合感染で危険。ワクチン接種が予防方法。成犬は通常症状が軽い。確定診断には検査が必要で、治療は症状に合わせた対処療法。ワクチン接種は予防の鍵。感染犬の隔離と衛生対策も重要。新型コロナウイルスとは異なるウイルス。 -
 犬の病気
犬の病気
犬パラインフルエンザウイルス感染症(CPIV)
犬パラインフルエンザウイルス感染症(CPIV)は、犬の呼吸器症状を引き起こす高度に伝染性のウイルス感染症。主な症状は咳、鼻水、発熱、食欲減退などで、混合感染が重症化させることもある。ワクチン接種が予防方法で、特に多頭飼育や他の犬と接触が多い場合は重要。疑いがある場合、診断と治療が必要。 -
 犬の病気
犬の病気
狂犬病ウイルス感染症
狂犬病は致死率100%の感染症で、動物や人に感染する恐ろしい病気。感染動物は暴力的になり、感染は咬傷や唾液伝播で広がる。予防には狂犬病ワクチン接種が必要で、発症前に接種することで予防可能。発症後の治療法はなく、感染者と接触した場合、予防接種が必要。狂犬病は全世界で毎年約3.5万〜5万人が感染により死亡し、予防が重要。発症例は日本では見られていないが、感染危険性があるため、狂犬病ワクチン接種は必須。 -
 犬の病気
犬の病気
犬パルボウイルス感染症
犬パルボウイルス感染症は激しい嘔吐と下痢を引き起こす病気。感染は口や鼻からウイルスを摂取し、糞便中にも存在。特に子犬が感染しやすく、犬種によって症状が悪化する可能性がある。ワクチン接種が予防に有効。感染犬の隔離と環境消毒が必要。母犬の免疫も考慮して接種回数に注意。ワクチンの効果は抗体検査で確認可能。感染犬の看護や食事療法が重要。パルボウイルス感染と将来の消化器疾患リスクの関連性にも注意。 -
 犬の病気
犬の病気
犬伝染性喉頭気管炎(CAV-2:犬アデノウイルス2型感染症)
犬伝染性喉頭気管炎(CAV-2)は犬の感染症で、犬アデノウイルス2型(CAV-2)感染による上部気道炎。ワクチンで予防可能。感染は咳やくしゃみ、飛沫物を介して拡がり、他の病気との混合感染で重症化することも。治療は対症療法や抗生物質。感染を防ぐためにワクチン接種が重要。感染犬を隔離し、環境消毒が必要。ウイルスは犬伝染性肝炎と同属で、感染後のウイルス排出が長期化するため、予防接種が勧められる。 -
 犬の病気
犬の病気
犬伝染性肝炎(CAV-1:犬アデノウイルス1型感染症)
犬伝染性肝炎は犬の感染症で、アデノウイルス1型(CAV-1)感染により肝炎を引き起こす。感染は糞尿や唾液を介して広がり、症状には嘔吐、発熱、下痢、肝臓機能障害が含まれ、致死率が高いこともある。ワクチン接種で予防可能で、感染犬の隔離と環境消毒が重要。ウイルスは外部でしばらく生存し、高温や塩素で死滅。治療は支持療法に頼る。