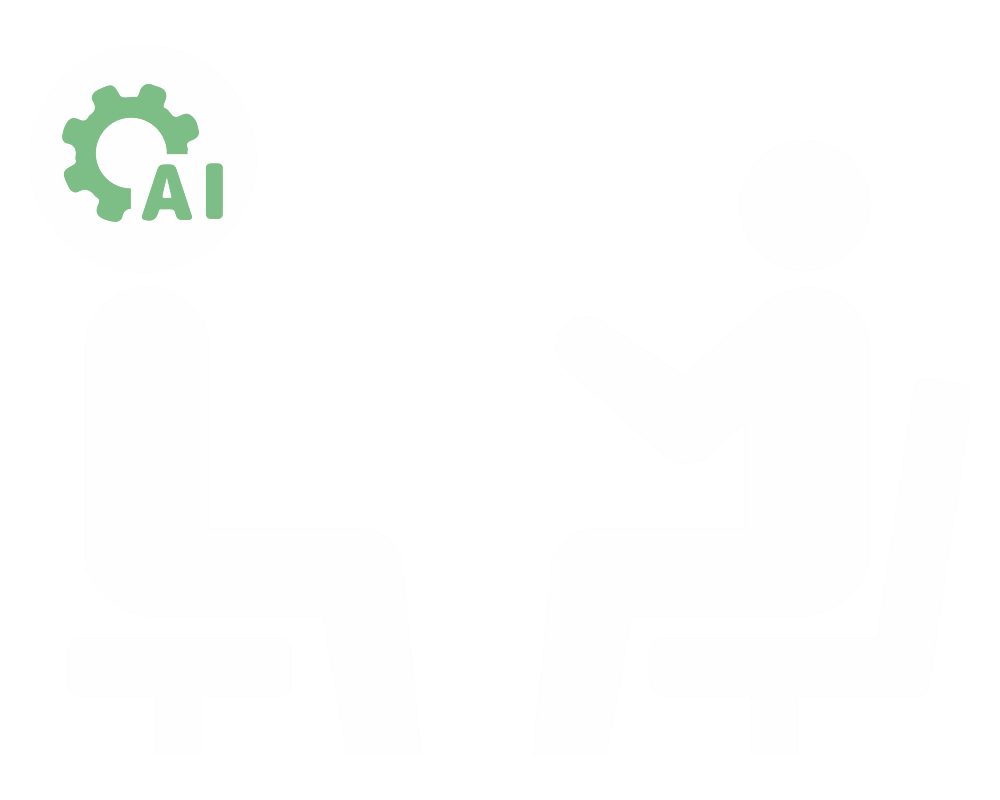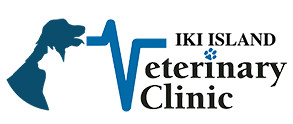-
 猫の病気
猫の病気
水頭症
脳の周りは、頭蓋骨との間に脳脊髄液と呼ばれる体液があり、クッションのような役割をして脳を守っています。水頭症(すいとうしょう)とは、この髄液が頭蓋内に過剰にたまり、脳が圧迫されて様々な症状が出る病気です。 マルチーズ、ヨークシャー・テリア、イングリッシュ・ブルドッグ、チワワ、ラサアプソ、ポメラニアン、トイ・プードル、ケアーン・テリア、ボストン・テリア、パグ、ペキニーズなど、一般にトイ種やミニチュア種、短頭種はリスクが高いと言われています。猫では稀な病気ですが、シャム猫に多く発症すると言われています。 -
 猫の病気
猫の病気
膝蓋骨脱臼(パテラ)
膝蓋骨脱臼(しつがいこつだっきゅう)とは、犬の後肢にある膝蓋骨(しつがいこつ:膝関節にあるお皿のような骨)が正常な位置から内側(小型犬に多い)、または外側(大型犬に見られる)に外れてしまう(脱臼)状態をいいます。膝蓋骨のことを英語でpatella(パテラ)ということから、動物病院ではよく膝蓋骨脱臼を「パテラ」と呼びます。猫の膝蓋骨脱臼は稀で、犬ほど多くありません。 この病気はどの犬種にも見られますが、45%は小型犬で、トイ・プードル、ポメラニアン、ヨークシャー・テリア、チワワ、マルチーズなどに多く見られます。85%は先天性で生まれつきです。90%は内側側に脱臼し、65%は両側に膝蓋骨脱臼が見られます。 -
 猫の病気
猫の病気
股関節形成不全
股関節形成不全(こかんせつけいせいふぜん)は、股関節形成異常や股関節異形成、股異形成などとも呼ばれ、股関節が発育の段階で形態的な異常を起こし、正常に形成されていないことや変形することにより、歩き方などに様々な異変を起こす病気です。遺伝(70%)や環境的要因(30%)が考えられ、おもにジャーマン・シェパード、ラブラドール・レトリーバー、ゴールデン・レトリーバー、ニューファンドランド、バーニーズ・マウンテン、ロット・ワイラー、セント・バーナード、グレート・ピレニーズ、アイリッシュ・ウォーター・スパ二エルなどの大型や超大型犬で多く見られる病気で、小型犬や中型犬で発症することは稀です。 一般的に両側の股関節に発症(93%)することが多いといわれておりますが、片側のみの場合もあります。 股関節形成不全は犬の病気のイメージが強いのですが、猫でも発症することがわかってきています。特にヒマラヤン、ペルシャ、メインクーンに多いとされてます。 -
 猫の病気
猫の病気
角膜炎
角膜炎(かくまくえん)は、角膜とはいわゆる黒目と呼ばれる部分の表面をおおっている角膜が何らかの原因で炎症を起こした状態ことです。シーズー、フレンチブルドッグ、パグなど鼻が短く眼が大きないわゆる短頭種と呼ばれる犬種は目をぶつけやすいため角膜炎が多く起こるといわれています。 -
 猫の病気
猫の病気
白内障
目には水晶体と呼ばれるカメラのレンズと同じ役目をする器官があります。本来は無色透明ですが、白内障になるとこの水晶体の一部もしくは全部が何らかの原因で変性し、白く濁ってしまいます。水晶体が濁ると光を透すことができなくなるため、視覚に影響が出てきます。水晶体の濁りが一部分であれば視野は欠けた状態ですが、水晶体全体が濁ってしまうと、全く見えなくなってしまいます。 基本的には進行性で、経過を見ていると視覚障害ばかりでは無く、濁った水晶体に起因する眼球内炎症(水晶体起因性ぶどう膜炎が起こり、ときには網膜剥離や緑内障へと進行することもあります。 -
 猫の病気
猫の病気
趾間皮膚炎/指間炎
趾間皮膚炎(しかんひふえん)とは、趾間、つまり肢先(あしさき)の指の間、人でいう手や足の指の間、肉球に炎症が起こり、犬や猫が舐めてしまって発赤、腫脹、脱毛、疼痛を伴う皮膚炎です。趾間炎とか指間炎、肢端皮膚炎とも言われます。 -
 猫の病気
猫の病気
肛門嚢炎/肛門嚢破裂
肛門嚢(こうもんのう)とは犬や猫の肛門の左右にある一対の袋状の器官です。その中にはイタチやスカンクのように独特の悪臭を放つ液体もしくはペースト状の貯留物が入っています。この貯留物は、排便時に肛門が圧迫された時や恐怖を感じた時、また、犬が肛門部を舐めることによっても排泄されます。この肛門嚢(腺)が何らかの原因で炎症を起こしてしまうことを肛門嚢(腺)炎といい、破裂して破れてしまうことを肛門嚢破裂といいます。 犬で多く発症する病気で、ミニチュア・プードル、トイ・プードル、チワワなど小型の室内犬に多い疾患です。猫でも稀にみられます。 -
 猫の病気
猫の病気
てんかん(癲癇)
癲癇(てんかん)とは、発作的に繰り返される全身性の痙攣(けいれん)や意識障害を主な症状とする脳疾患で、繰り返し起こります。犬において最も一般的な発作の原因といわれています。てんかん発作の発症は5歳になるまでみられないこともありますが、一般に6ヶ月〜3歳齢の間に初めて起こることが多いようです(一次性てんかん)。 犬ではの発症率は0.55〜2.3%ですから100頭に1頭程度、猫では0.3〜1.0%ですので、100頭に1頭以下くらいです。 -
 猫の病気
猫の病気
マッサージ療法
マッサージ療法とは筋肉などの軟部組織を優しく手で触って行う治療的操作で、リハビリテーションの一つです。自宅でも適切な時期に正しい方法で行えば、治療の助けになります。注意して頂くのは人間のマッサージ法とは同じ部分もあるし、異なる部分もあることです。 動物のリハビリは獣医師だけでなく、獣医医療スタッフやペットオーナーが一体になりチーム意識を持って治療に臨むことが重要です。 以下、マッサージ療法を解説しておきますので、ご自宅での参考にしてください。なお、これ以降のコンテンツは壱岐動物病院をご利用のペットオーナー様への公開となります。マッサージ療法に関しましては、必ず数回は動物病院できちんとした資格(CCRP)を取得している獣医師、獣医看護師、PTなどの施術や指導を受けた後に行うようにしてください。 -
 猫の病気
猫の病気
アレルギー性皮膚炎
アレルギー性皮膚炎は、アレルギー反応によって引き起こされる皮膚の炎症で、アレルギー症状を引き起こすアレルゲンに対する過剰な免疫応答によって生じます。アレルゲンはハウスダスト、花粉、カビ、ダニ、ノミ、食物などさまざまなもので、痒みが主な症状で、皮膚の赤み、脱毛、発疹なども見られます。診断にはアレルギー検査が使用され、治療にはアレルゲンの特定と除去、抗ヒスタミン剤、副腎皮質ホルモン剤、免疫抑制剤の使用が含まれます。また、予防にはノミ駆虫剤の定期的な使用が重要であり、食事によるアレルギーの場合は特定の食事療法が考えられます。診断や治療には獣医師の指導が必要です。 -
 猫の病気
猫の病気
アトピー性皮膚炎
アトピー性皮膚炎は、犬や猫においてアレルギー物質に対する過剰な免疫反応により、かゆみや皮膚炎が発生する疾患。原因は主に環境中のアレルギー源(花粉、ダニ、カビなど)と遺伝的要因が結びついて発症。症状にはかゆみ、発疹、脱毛が含まれ、治療は抗ヒスタミン薬、ステロイド剤、抗生物質、シャンプー、免疫療法などが用いられる。完治は難しく、症状のコントロールが主要。アレルゲンの除去や皮膚ケアも重要。環境中のダニなどを掃除し、食事にも注意が必要。 -
 猫の病気
猫の病気
消化管内異物
消化管内異物は、誤って摂取した異物が食道、胃、小腸、大腸などの消化管内に留まる状態。誤飲の原因となり、異物の種類によりさまざまな症状が現れます。診断には検査が必要で、治療には観察、催吐、内視鏡、手術などが含まれます。異物の中毒や毒性を考慮する場合もあります。予防策として、異物へのアクセスを制限し、異食の癖に気をつける必要があります。再発性が高く、再度摂取した場合は緊急処置が必要です。