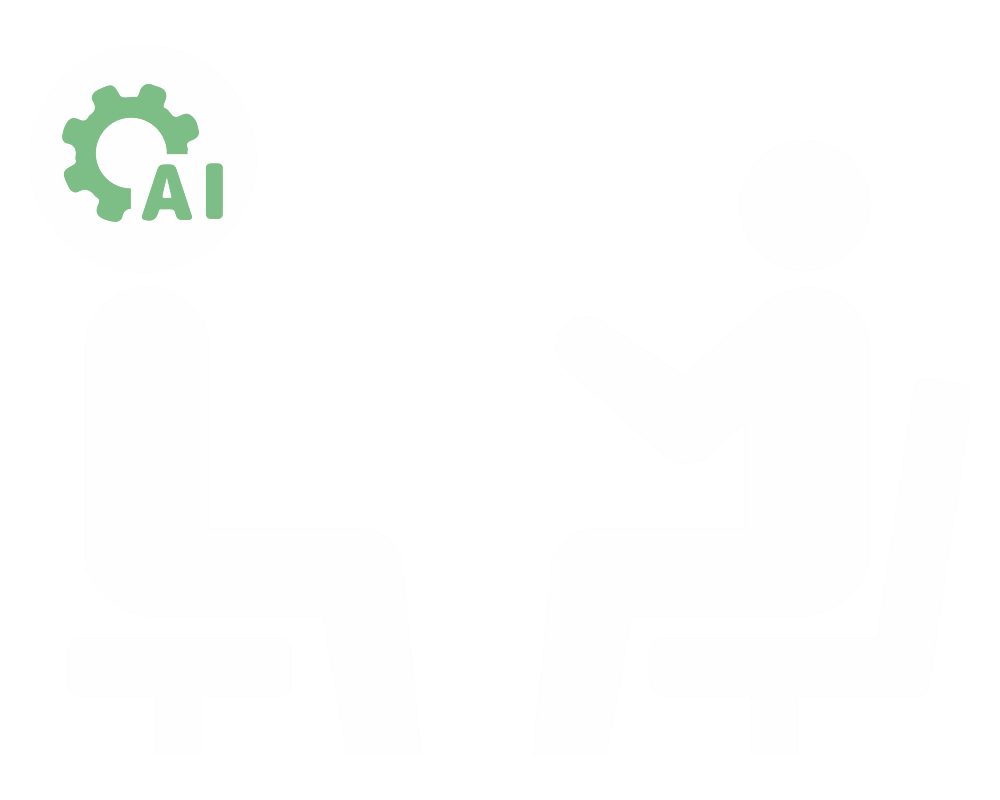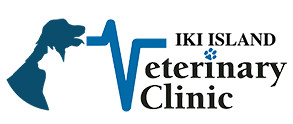-
 寄生虫科(猫)
寄生虫科(猫)
コクシジウム症:Coccidiosis
コクシジウム症は、犬や猫の腸に寄生する単細胞の寄生虫であるコクシジウムによって引き起こされる感染症です。特に子犬や子猫、免疫力の低下した動物で問題となりやすく、宿主の腸の細胞に侵入してそこで増殖することで症状が現れます。これらの寄生虫は主にシストイソスポーラ属のCystoisospora felisとCystoisospora rivoltaによって引き起こされ、人や犬には感染しません。ただし、トキソプラズマ属は人畜共通感染症を引き起こすことがあり、これとは区別されます。 -
 寄生虫科(猫)
寄生虫科(猫)
壺型吸虫:Pharyngostomum cordatum
壺型吸虫症は、猫の小腸に壺型吸虫が寄生する疾患で、感染が水田や地方都市で発生することが多い。感染源はカエルやヘビの捕食による中間宿主から発生し、感染症状には慢性の下痢、体重減少、栄養不良、幼若動物の発育不全が含まれる。診断は糞便検査で虫卵を探し、治療は駆虫薬により行われる。予防には室内飼育、中間宿主の捕食防止が効果的で、定期的な駆虫がお勧めされる。糞便の異常があれば動物病院で検査を受けるべきで、人間への感染は報告がない。 -
 寄生虫科(猫)
寄生虫科(猫)
シラミ症
シラミ症(しらみしょう)とは、皮膚や毛へのシラミの外部寄生のことを言います。屋外飼育や捨てられたりして、環境が悪い場合など犬猫に見られます。猫ではどちらかとおうとシラミよりみハジラミの寄生が多く見られます。 -
 寄生虫科(猫)
寄生虫科(猫)
猫回虫症
回虫(かいちゅう)は線虫類に属する寄生虫です。人や犬、猫をはじめ、多くの哺乳類の主にに小腸に寄生します。犬科の動物には犬回虫、猫科の動物には猫回虫、人には人回虫というように、それぞれのどうぶつに固有の回虫が存在ます。 -
 寄生虫科(猫)
寄生虫科(猫)
トキソプラズマ症
トキソプラズマは、原虫と呼ばれる顕微鏡でみなければみえないような小さな寄生生物で、世界中の猫(ネコ科動物)、豚、犬、鳥類などに感染がみられます。この原虫は人間にも感染し、人と動物の共通感染症(ズーノーシス)ですので、注意が必要です。しかしながら、大部分は症状が出ない不顕性(ふけんせい)感染であり、日本人では成人の20〜30%がすでにトキソプラズマに対する抗体を持っていることが知られています。 妊娠初期の女性がトキソプラズマ症に初感染すると胎児にも感染し、流産や死産などの原因にもなる可能性があるので注意が必要です。 -
 寄生虫科(猫)
寄生虫科(猫)
毛包虫症(アカラス)
毛包虫は別名で「ニキビダニ」や「アカラス」ともいわれます。動物の毛包内(毛穴)に寄生するダニの一種です。実は毛包虫は健康な動物の皮膚にも少し常在していて、ふつうは病気の原因とならなりません。しかし、免疫力が低下したりや遺伝的な要因などによって多数増殖してしまった場合、毛包虫症として発症することが多くあります。 毛包虫による皮膚炎は、局所性に出る場合と全身性に出る場合があります。さらに3〜12カ月齢で発症する若年性と1歳以降で発症する成犬の毛包症に分かれます。 -
 寄生虫科(猫)
寄生虫科(猫)
瓜実条虫症
瓜実条虫(うりざねじょうちゅう)症は、ウリの種が連なっている形をした瓜実(うりざね)条虫(サナダ虫)が小腸に寄生することによって起こる病気です。瓜実条虫はその虫卵を食べたノミやシラミの体内で発育し、グルーミングなどで犬や猫がノミを誤って飲み込むと同時に感染します。犬、猫、フェレットだけでなく、人にも感染するズーノーシス(人獣共通感染症)です。 -
 寄生虫科(猫)
寄生虫科(猫)
マンソン裂頭条虫症
マンソン裂頭条虫(まんそんれっとうじょうちゅう)症とは、犬や猫の小腸にマンソン裂頭条虫が寄生する病気です。1882年にパトリック・マンソンにより発見されたためこの名前で呼ばれているようです。ほとんどの場合は寄生しても無症状ですが、多数寄生した場合は下痢などの消化器症状が現れることもあります。 人間も感染する寄生虫ですが、犬や猫から移ることはありません。日本国内では猫での発生が多く、地域によっては30〜45%と高い感染率を示します。犬ではほとんどの地域で数%程度です。また、中間宿主の減少により都市部では近年ほとんど感染例がなく、地方都市や郊外での発生が多い寄生虫です。壱岐でも多く見かけます。 -
 寄生虫科(猫)
寄生虫科(猫)
猫小穿孔ヒゼンダニ症/猫疥癬症
猫疥癬症(ねこかいせんしょう)は、猫ヒゼンダニ(猫小穿孔ヒゼンダニ)というダニによって起こる皮膚病です。このヒゼンダニは皮膚にトンネルを作って寄生するため、激しい痒みや皮膚炎を起こします。 伝染性がとても強く、感染している猫との接触や多頭飼育の場合、ブラシやタオルの共有などによっても感染します。また、感染した猫ちゃんを抱っこすることなどで、人にも感染する人獣共通感染症:ズーノーシス(zoonosis)であり、感染すると腕やお腹などに発疹ができて強い痒みの症状がみられる場合があります。特に抵抗力の弱い病人や子供、老人などが感染すると症状が重くなるため注意が必要です。 -
 寄生虫科(猫)
寄生虫科(猫)
犬フィラリア症:犬糸状虫症
犬フィラリア症は、犬の心臓に寄生する寄生虫による感染病で、蚊を介して広がります。症状は初期には気づかれず、後に呼吸困難や心臓、肝臓、腎臓の障害を引き起こし、死亡率が高いです。人や猫にも感染する可能性があります。予防薬や予防注射で予防可能で、感染が疑われる場合は検査が必要です。予防が最善です。血液検査で感染を調べ、予防薬の定期投与が重要です。