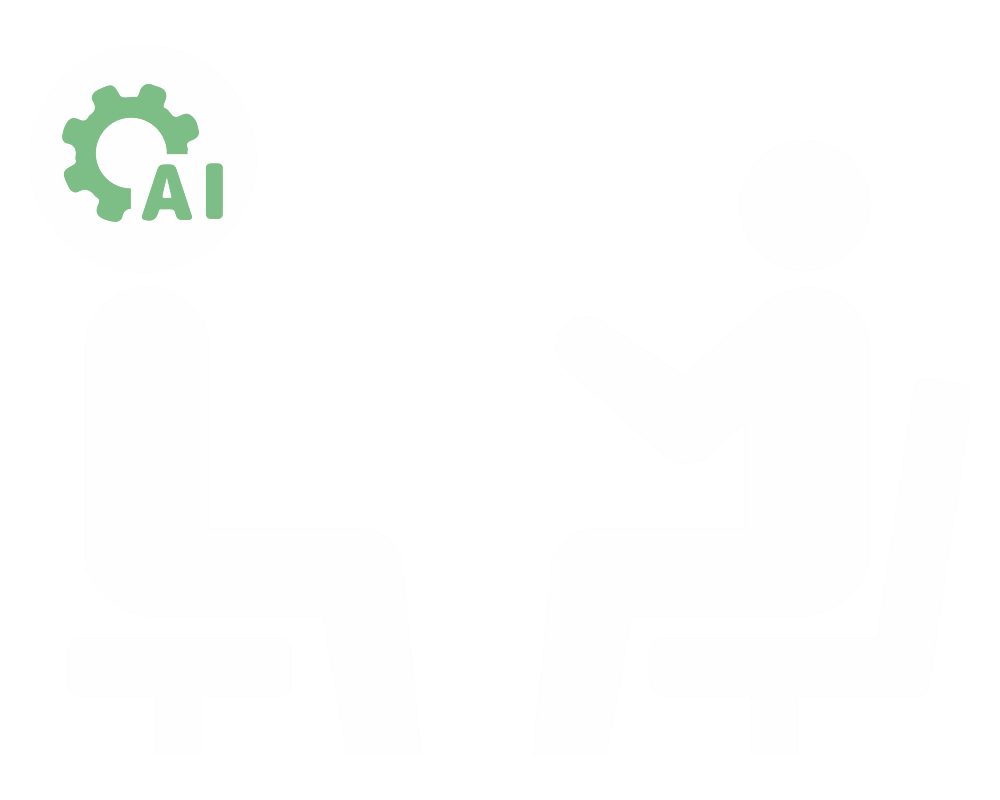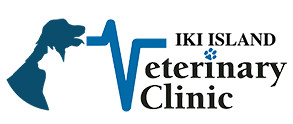-
 消化器科(犬)
消化器科(犬)
便秘:Constipation
愛犬や愛猫が何日も排便をしていなかったり、排便時にいきんで苦しそうにしている姿を見かけたことはありませんか?それは「便秘(べんぴ)」と呼ばれる状態かもしれません。便秘とは、通常よりも排便の回数が減ったり、便が硬くなって出しづらくなったりすることで、排便が困難になる症状です。さらに進行すると「重度便秘」と呼ばれ、腸内に糞便が強く詰まり、自然には排泄できないほど深刻な状態になることもあります。便秘が長引くと、大腸が広がり「巨大結腸症」という慢性的な疾患へと進行することもあります。 -
 消化器科(犬)
消化器科(犬)
胆嚢破裂:Biliary Tree Rupture
胆嚢破裂とは、胆嚢の壁が損傷し、胆汁が腹腔内に漏れ出す状態を指します。胆汁は本来、肝臓で生成され、胆嚢に蓄えられた後、食事の消化を助けるために小腸へ分泌されます。しかし、胆嚢が破裂すると、胆汁が腹腔内に広がり、重篤な炎症である胆汁性腹膜炎を引き起こします。この状態は放置すると命に関わるため、迅速な診断と治療が必要です。 -
 消化器科(犬)
消化器科(犬)
急性腹症:Acute Abdomen
腹部に生じる痛みを「腹痛(ふくつう)」と言いますが、突然おなかが激しく痛くなることを、急性腹症(きゅうせいふくしょう)と言います。この急性腹症には緊急手術を含む迅速な対応が必要となる重篤な病気が隠れていることもありますので注意が必要です。特に日頃から言葉を発しない動物の場合、この急性腹症にペットオーナーが気づいてあげる必要があります。 -
 消化器科(犬)
消化器科(犬)
胆泥症
胆嚢(たんのう)とは、肝臓に付属する袋状の構造物です。肝臓で作った脂肪の消化に重要な役割を果たす胆汁を蓄えて、濃縮しています。食事すると胆嚢が収縮し、それに伴い胆汁は総胆管を通って十二指腸に放出されます。 胆泥(たんでい)症とは、何らかの原因でこの胆汁が濃縮して変質し、正常な胆汁とは異なる胆泥とよばれる泥状になったものが胆嚢に貯留した状態をいいます。 胆汁の成分が変質して結石になったものを胆石といいますが、犬では胆石症の発生は比較的まれで、胆泥症の方が多く見られます。また、胆泥は変化が進むと胆嚢粘液嚢腫に発展する可能性があるとされています。 -
 消化器科(犬)
消化器科(犬)
家庭でできるアレルギー対策
花粉アレルゲン 原因植物の花粉飛散時期を把握し、花粉情報に注意し、対処することが大切です。テレビ・ […] -
 消化器科(犬)
消化器科(犬)
異物誤飲(誤飲・誤食)
動物は時に人が思ってもみないものを食べたり飲み込んだりしてしまうことがあります。これを異物誤飲(いぶつごいん)と言い、特に子犬や子猫は、好奇心旺盛で色々なものを誤って飲み込んでしまうことが多いので注意が必要です。データでは異物誤飲は、1歳以上の動物と比べ1歳未満ののほうが4倍も高いことがわかっています。 飲み込んでしまうものは石やおもちゃ、衣類など様々で、症状や重篤度は飲み込んだものにより違います。 -
 消化器科(犬)
消化器科(犬)
膵炎(犬編)
膵炎(すいえん)とは、膵臓に炎症が起こる病気のことで、大きく分けて「急性膵炎」と「慢性膵炎」があります。中齢〜高齢の肥満した雌に多く発症する傾向があると報告されています。犬種では、急性膵炎は、ミニチュア・シュナウザー、ヨークシャー・テリア、その他のテリア種にも多いと言われ、慢性膵炎は、イングリッシュ・コッカー・スパニエル、キャバリア・キングチャールズ・スパニエル、ボクサー、ラフ・コリーなどに多いと言われています。 膵臓では、非常に強力な消化酵素(アミラーゼ、リパーゼ、トリプシンなど)が作られ、「タンパク質や脂肪、炭水化物を分解し、血糖値をコントロールするためにインスリンを出す」などの役割を担っています。 これらの消化酵素は通常、膵臓を傷つけないよう十二指腸へ運ばれてから活性化します。しかし、なんらかの原因で消化酵素が膵臓内で突然活性化することで、自分で自分の膵臓を消化してしまい、傷つけてしまうことで「急性膵炎(きゅうせいすいえん)」が起こります。症状が重いものでは膵臓の炎症が他の臓器に広がり、肝臓や腎臓の障害も引き起こすことがあります。さらに、重症では全身の血管内で微小な血栓が形成され、それが血管内で詰まるってしまうDIC(播種性 -
 消化器科(犬)
消化器科(犬)
カンピロバクター症
カンピロバクターは螺旋状またはS字状に湾曲した細菌で、回転運動を行いながらすばやく動きます。人では食中毒の原因となる代表的な菌で、細菌性腸炎を起こします。カンピロバクター菌に汚染されてしまった食べ物を食べたり、飲んだりして感染し、キャンピロバクター症とも言われます。 カンピロバクター菌は自然界のあらゆるところに生息しており、人にも感染し(人と動物の共通感染症)、多頭飼育の場合は特に他の動物へも感染が起こりやすくなります。犬や猫の腸管に常在していますが、保菌率はそれほど高くない(1%前後)とされています。また、免疫力の低い子犬や子猫、ストレスの多い環境下や免疫力が低下しているときに発症することがあります。 -
 消化器科(犬)
消化器科(犬)
蛋白喪失性腸症:PLE(Protein-Losing Enteropathy)
蛋白漏出性腸症(たんぱくろうしゅつせいちょうしょう)とは、その英語の頭文字をとってPLEとも呼ばれ、腸から多量の蛋白が漏れ出てしまう病気です。それによって、血液中のタンパク質が少なくなり、低蛋白血症を起こします。 蛋白漏出性腸症は、厳密には特定の病名を指すわけではなく、さまざまな消化管(慢性下痢など)の疾患から引き起こされる状態を言います。 性別や年齢を問わず発症し、犬に多く見られ、猫では稀な病気です。特に多くもいられる犬種は、ヨークシャー・テリア、アイリッシュ・ソフトコーテッド・ウィートン・テリア、ロットワイラー、ジャーマン・シェパード・ドッグなどに多く見られるという報告があります。 -
 消化器科(犬)
消化器科(犬)
胃拡張捻転症候群:Gastric dilatation Volvulus(GDV…
胃拡張捻転症候群とは? 胃拡張・胃捻転症候群(いかくちょう・いねんてんしょうこうぐん)は、食べ物や […] -
 消化器科(犬)
消化器科(犬)
胆嚢粘液嚢腫
胆嚢とは、肝臓にくっついている袋状の構造物で、肝臓で作った脂肪の消化に重要な役割を果たす胆汁を蓄えて、濃縮しています。食事をするとこの胆嚢が収縮し、収縮に伴い、胆汁は総胆管を通って十二指腸に放出されます。 胆嚢粘液嚢腫(たんのうねんえきのうしゅ)とは、何らかの原因で胆嚢の中にゼリー状の粘液物質(ムチンという糖タンパク質)が貯留した状態をいいます。また、胆泥症から胆嚢粘液嚢腫になる事もあります。粘液物質が増加すると胆汁の分泌を障害するために様々な消化器症状を引き起こし、状態が進むと、黄疸や胆嚢破裂に伴う腹膜炎などの重篤な合併症を引き起こします。 中〜高齢の犬に多く見られ、猫では稀な病気です。 -
 消化器科(犬)
消化器科(犬)
臍ヘルニア
通常胎児期に開いている臍輪は分娩時にはしっかりと閉じてその跡のみが残るものです。これを一般には臍(へそ)といいます。臍(さい)ヘルニアとは、おへその臍輪からお腹の中の大網や腸管などが脱出して腹壁の皮下に入り、おへその部分で隆起する疾患で、先天性(生まれたときから)と後天性(生後や大きくなってから)に分けられますが、多くは先天的に起こっているものがほとんどです。俗にいう「出べそ」とは、臍ヘルニアのことをいいます。 人間でいういわゆるデベソと同じようなものですが、人間の赤ちゃんが生後1年くらいまでに90%なくなるのに比べて犬や猫の場合は自然治癒するものもありますが、人に比べると少ないようです。ただ、痛みを伴わず、好発犬種でもない場合は、放置しておいても生後6カ月の間に自然閉鎖することもあります。 臍ヘルニアには、還納性(デベソ」を押すとお腹の中にもどる)が認められないものは、「そもそもヘルニアの可能性が低い」か、緊急性の高いヘルニアと考えられるため注意が必要です。 なお、一部の品種では遺伝が関与していると考えられています。