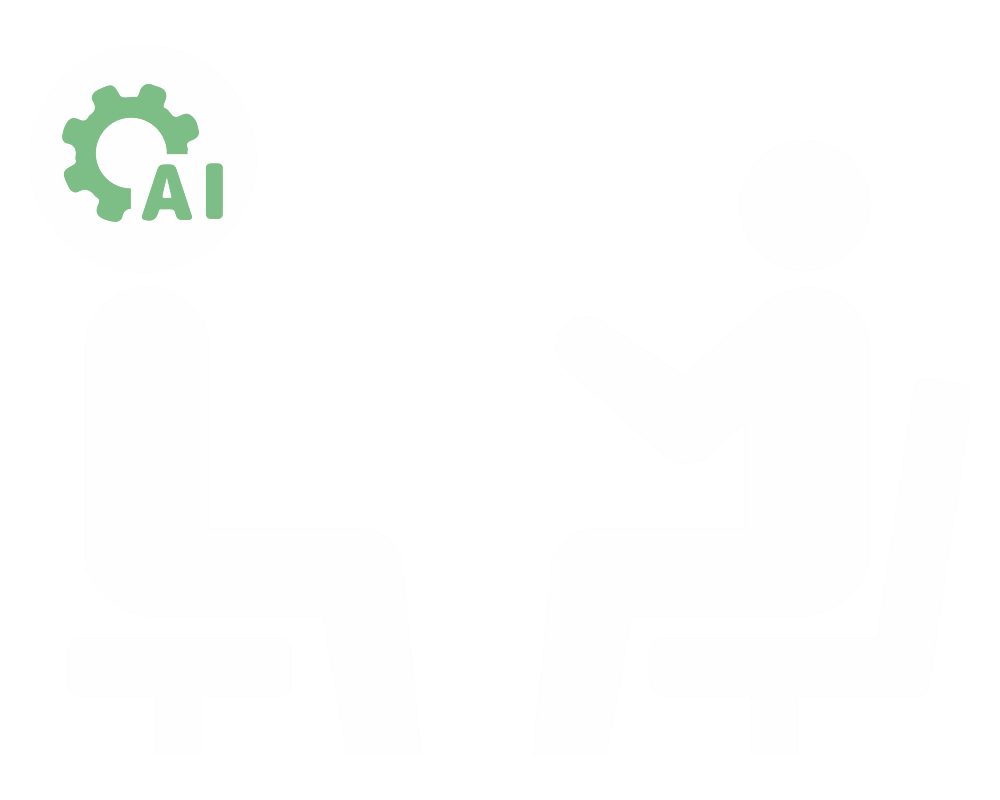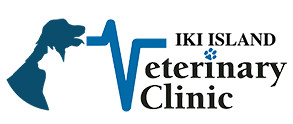-
 犬の病気
犬の病気
発熱
発熱(はつねつ)とは、病気に伴う兆候や症状の一つで、動物病院では熱発(ねっぱつ)とも言います。発熱は、生理的や深刻ではないものから生命を脅かすものまで、さまざまな原因によって引き起こされます。 犬や猫の平熱は人よりも高く、大体38.3度から38.8度くらいです。個体差があるので、日頃から体温測定をしてその子の平熱を知っておくことがとても大切です。平熱を大きく上回る(もしくは下回る)場合は、すぐに当院にご相談ください。通常平熱を0.5℃上回る39.3℃(または下回る:37.8℃以下)以上の場合は異常がかくれているかもしれません。40℃を超すと確実に熱があるといえますので、すぐにご相談ください。 -
 犬の病気
犬の病気
亜鉛中毒
※電話などでの各種病気に関するお問い合わせは、通常診療業務に支障をきたしますので、当院をご利用のペッ […] -
 犬の病気
犬の病気
黄疸:Jaundice
黄疸(おうだん)とは、胆汁色素であるビリルビンが過剰に産生されたり、排泄能力の低下により、血液中にビリルビンが増加して、皮膚や粘膜、血清などが黄染(黄色くなること)することをいいます。 ビリルビンは、赤血球中の血色素であるヘモグロビンが分解されたときに生じます。このビリルビンは、肝臓で処理された後、胆汁とともに胆嚢に貯蔵され、腸管内に排泄されます。その後、腸内の細菌によって分解され、便や尿とともに体外に排出されます。 黄疸は病気の名前ではなく症状の一つですので、そのため、ビリルビン増加の原因となる疾患を特定し、治療にあたることが重要になります。 -
 犬の病気
犬の病気
ぶどう膜炎
目の組織のうち、瞳孔(黒目のこと)の周りの眼球の色がついている部分である「虹彩(こうさい)」、水晶体を取り囲んで水晶体の厚みを調節する毛様体筋がある「毛様体(もうようたい)」、強膜(白目のこと)の内側にある膜である「脈絡膜(みゃくらくまく)」を総称して「ブドウ膜」といいます。「ブドウ膜」には目に栄養を与えるための毛細血管が分布しており、眼球の内部を覆っています。何らかの原因により、このブドウ膜の一部もしくは全体に炎症が起きるのがブドウ膜炎です。 -
 犬の病気
犬の病気
熱中症(熱射病:Heatstroke)
熱中症とは日射病や熱射病などの総称で、夏場などの温度や湿度が高い時期(5月から10月)に特に注意をしたい病気です。直射日光や温度や湿度の高い環境下に長時間いたり、そのような環境下で運動を続けることにより体温が上昇します。すると、人間と同じような汗をほとんどかかなので体温調節機能が正常に機能しなくなり、異常に体温が上昇(40.5℃以上)してしまいます。 実は真夏より、動物の体が暑さに順応する前の初夏に多いので注意してください。 特に、シーズー、パグ、フレンチブルドック、ブルドック、ペキニーズなどの短頭種、それに日本の保険会社の統計ではゴールデン・レトリバー、ラブラドール・レトリバーも多いとされています。猫ではペルシャやエキゾチック・ショートヘアー、ヒマラヤン、さらに肥満気味の犬猫、加齢(高齢)、心臓病や呼吸器の持病が有る場合などに起こりやすいといわれているので注意が必要です[1]。 猫は犬に比べて熱中症には強いとされていますが、それでも夏場の締め切った室内などでは起こるので注意が必要です。 -
 犬の病気
犬の病気
犬の保険請求理由TOP30 2012年版
※平均診療金額はアニコムの資料では平均保険受給額(50%プラン)となっているものを2倍にしてあります […] -
 犬の病気
犬の病気
痴呆(認知症:認知機能不全症候群)
「痴呆(ちほう)」とは一般には「ボケ」とも言われます。これは、発育した脳が加齢などにより損傷されて、それまでに獲得していた知的能力が低下してしまっている状態で、現在では「認知症(にんちしょう)」「認知機能不全症候群(にんちきのうふぜんしょうこうぐん)」などとも言われます。 近年では獣医療の進歩に伴いワンちゃんや猫ちゃんの高齢化が進み、その結果、老齢に伴う認知症が増加しています。カリフォルニア大学の研究では11〜12歳の約28%、15〜16歳の約68%の犬に認知機能障害が現われると報告されています。猫では11〜14歳の約30%、15歳以上の約50%で見られるとされています。 また、犬では小型犬に多く、雄(オス)よりも雌(メス)に多く、未去勢雄よりも去勢雄に多い(長生きするから?)と報告されています。また、てんかんを持っていると発症しやすいとの報告もあります。 さらに、好発犬種としては柴犬や日本犬系の雑種がなりやすいと言われてますが、そうではなく年齢(加齢)が大きなリスク要因であるとする報告もあります。 以前は、犬の痴呆症は人とお -
 犬の病気
犬の病気
副腎皮質機能低下症(アジソン病)
副腎皮質機能低下症(ふくじんひしつきのうていかしょう)は俗に「アジソン病」と呼ばれることもあります。副腎は、左右の腎臓の近くにあり、副腎皮質ホルモン(コルチゾール)を分泌する大切な内分泌器官です。このコルチゾールは、糖代謝や脂質代謝、タンパク質代謝、体の免疫系やストレスに対する作用などさまざまな働きを担っています。 副腎皮質機能低下症になると、この副腎皮質ホルモンの分泌が低下することにより、さまざまな症状が引き起こされます。若齢〜中年齢(平均約 4 歳齢)の雌犬(特に避妊手術をしていない雌)で多く、海外では純血種に多いと言われています。猫では珍しい病気です。 -
 犬の病気
犬の病気
子宮蓄膿症
子宮は、雌(メス)犬や猫の腹腔内にあるY字型の生殖器官です。子宮蓄膿症(しきゅうちくのうしょう)とは、この子宮内に細菌感染が起こることで膿が溜まり、さまざまな症状を引き起こす病気です。猫に比べると犬に多く見られ、女性ホルモンの影響を受けやすく、特に子宮粘膜が増殖している発情後期に細菌感染が起こりやすいため、避妊手術をしていない中高齢での発症が多い病気です。避妊手術をしていないメス犬では最大19%程度が10歳までにこの病気になると報告されています。通常の子宮はもし細菌が侵入しても防御システムが働き排除できるのですが、発情出血後の発情休止期にはこの防御システムがうまくいかず感染が成立してしまいます。そのため、だいたいこの病気の数週間前に発情がきていることがおおい病気です。 また、子宮蓄膿症の発症には卵巣からのホルモンの分泌が関係しており、卵巣摘出を行っていればほとんど発症せず、当たり前ですが卵巣子宮摘出をしている場合には発症しません。 経産の犬よりも未経産の犬で多いと言われています。 -
 犬の病気
犬の病気
眼球突出
眼球突出(がんきゅうとっしゅつ)とは眼球脱出(がんきゅうだっしゅつ)とも言われ、眼球のサイズは正常で一部が出てしまっていることをいいます。正確には眼窩(がんか:眼球のはいっている頭骨の穴)から半分以上出ると眼球脱出になります。 眼球突出が起こりやすい犬種にはチワワ、フレンチブルドッグ、パグ、シーズー、ヨーキー、マルチーズで、特にチワワは外傷性の眼球突出が多くみられます。これは頭蓋骨(とうがいこつ:ずがいこつ)の形が一つの要因になっていると考えられます。人では事故などでかなり大きな力が加わらなければ眼球突出が起こることはないのですが、犬では比較的よく遭遇します。これは人と犬では頭蓋骨の形が異なっているためです。 -
 犬の病気
犬の病気
門脈体循環シャント
門脈体循環シャントは、「門脈体循環短絡症」、「門脈シャント」、「PSS」などと呼ばれこともある病気で、肝臓に入るはずの門脈という血管に余分な血管(シャント)ができて、肝臓を迂回してしまう血管奇形です。 通常、栄養やアンモニアなどの毒素は腸管から吸収され、門脈と呼ばれる血管を通って肝臓に運ばれ、利用されたり、無毒化されます。しかし、この門脈と全身の静脈の間をつなぐシャント(バイパス血管)があると、肝臓を通るはずの栄養や無毒化されるべき有害物質が肝臓を通らないで全身を回ってしまい、さまざまな障害や症状が引き起こされ、最悪の場合死に至ることもあります。 以前は、非常に珍しい疾患として考えられていましたが、現在増加傾向にあります。特に犬に多く見られ、猫では稀な病気です。 -
 犬の病気
犬の病気
肝外胆管閉塞
※電話などでの各種病気に関するお問い合わせは、通常診療業務に支障をきたしますので、当院をご利用のペッ […]