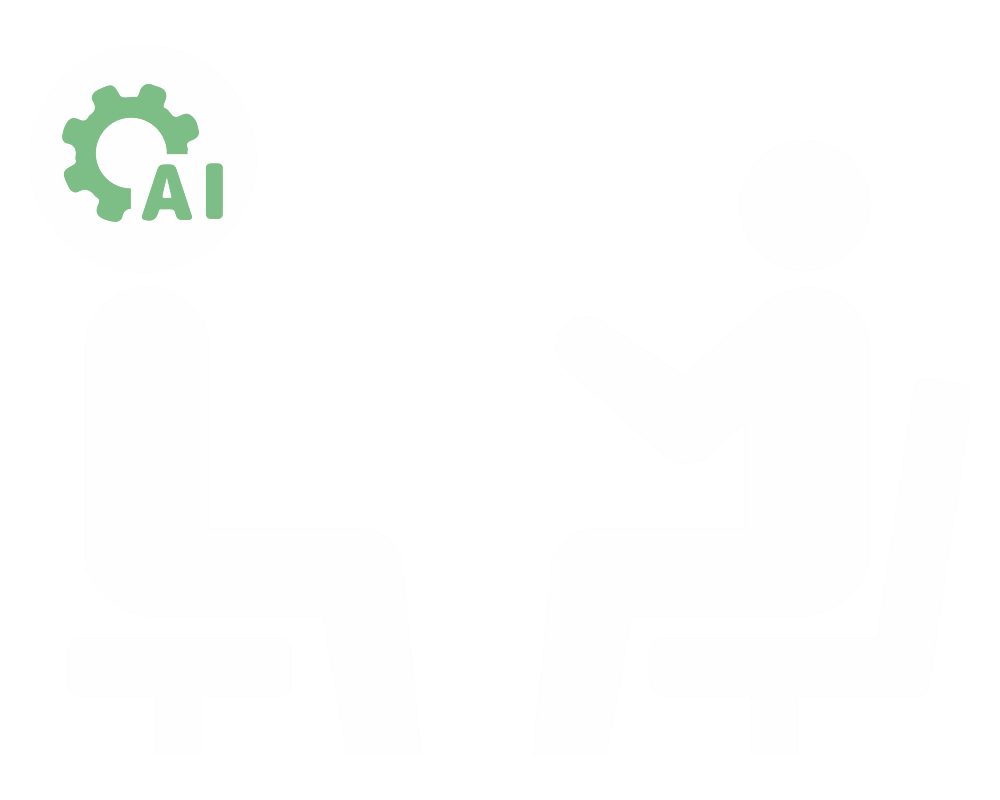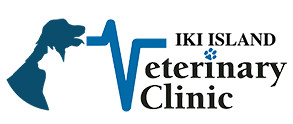-

尿蛋白(尿タンパク)
尿タンパク(にょうたんぱく)とは尿中(オシッコ)に排泄される蛋白のことです。正常な尿には蛋白はほとんど含まれないか、あるいは全く含まれません。主に腎臓の病気の判定に利用される指標の一つが、この尿蛋白(にょうたんぱく)です。尿蛋白は蛋白尿(たんぱくにょう)ともいいます。蛋白尿の殆どはタンパク質の中のアルブミンです。 -

犬ブルセラ症
犬ブルセラ症はブルセラ・カニス(Brucella canis)という細菌による人と動物の共通感染症(Zoonosis)です。ブルセラ症には他にもBurucell.abortus(主に牛) 、Burucell.suis(主に豚) 、Burucell.melitensis(主に山羊、羊) などもありますが、日本では1970年代にほぼ撲滅されています。別名でマルタ熱、波状熱、ジブラルタル熱と言われることもあります。 国内では2003年の静岡の繁殖施設の51頭、2005年の沖縄の繁殖施設の16頭、2006年の大阪の繁殖施設の139頭、2008年の愛知のペットショップ兼繁殖施設の15頭、2008年の東京などのドッグレンタル店の18頭など時々集団感染も見受けられます。また、1999年4月から四類感染症に感染症法によって指定されています。 -

汎骨炎
汎骨炎(はんこつえん)とは、特に中型〜大型の若い犬に見られる骨の炎症です。2歳齢未満の雄(オス)犬に多いと言われています。主に前肢(前足)に起こることが多い病気ですが、後肢(後足)でも起こることがあり、1本あるいは複数の足で同時に発生します。 -

新型コロナウイルス感染症:COVID-19
新型コロナウイルス(COVID-19)は主に人から人へと広がるウイルス感染症ですが、稀に犬や猫も、新型コロナウイルスに感染しています。感染は、動物が新型コロナウイルスに感染した人々と密接に接触した後に発生しています。 香港[2]、米国[3]、ベルギー[6]、フランス[7]、イギリス[8]など多くの国で伴侶動物として飼育されている犬や猫で、検査陽性反応が出ています。また、日本でも2020年8月、9月に犬の検査陽性が合計3頭確認されています[10][11]。 現在までに入手できる情報が限られてますが、新型コロナウイルスがペットとして飼育されている犬や猫を介して人に拡散するという報告はありませんが、人から動物に拡散したと思われる事例は複数報告されています[12]。 -

犬伝染性気管気管支炎:ケンネルコフ
ケンネルコフは、犬伝染性気管気管支炎といわれ、咳を主な症状とした伝染力の強い呼吸器の感染症です。ケンネルとは犬舎のことで、コフとは咳です。犬舎など多頭飼育の場所で起こりやすかったことからこう呼ばれるようになりました。犬伝染性呼吸器病とも言われることがあります。 この病気は、単一の病原体によるものではなく、いくつもの細菌やウイルスなどが複合して感染し、病気を起こしています。中でも重要なのが気管支敗血症菌(ボルデテラ)と呼ばれる細菌で、それにジステンパーウイルス、アデノウイルス1型、アデノウイルス2型、イヌパラインフルエンザウイルス、犬ヘルペスウイルスなどが関係します。イヌパラインフルエンザウイルスはケンネルコフの原因ウイルスとして最も検出頻度の高いウイルスですが、非常に弱いウイルスです。アデノウイルス1型は犬伝染性肝炎ウイルスと同様です。これらのウイルスは飛沫中に含まれて空気中を飛ぶために感染力が強く、犬の呼吸器系に感染します。しかしながら致死的な感染になることは少ないとされてます。 -

トキソプラズマ症
トキソプラズマは、原虫と呼ばれる顕微鏡でみなければみえないような小さな寄生生物で、世界中の猫(ネコ科動物)、豚、犬、鳥類などに感染がみられます。この原虫は人間にも感染し、人と動物の共通感染症(ズーノーシス)ですので、注意が必要です。しかしながら、大部分は症状が出ない不顕性(ふけんせい)感染であり、日本人では成人の20〜30%がすでにトキソプラズマに対する抗体を持っていることが知られています。 妊娠初期の女性がトキソプラズマ症に初感染すると胎児にも感染し、流産や死産などの原因にもなる可能性があるので注意が必要です。 -

カンピロバクター症
カンピロバクターは螺旋状またはS字状に湾曲した細菌で、回転運動を行いながらすばやく動きます。人では食中毒の原因となる代表的な菌で、細菌性腸炎を起こします。カンピロバクター菌に汚染されてしまった食べ物を食べたり、飲んだりして感染し、キャンピロバクター症とも言われます。 カンピロバクター菌は自然界のあらゆるところに生息しており、人にも感染し(人と動物の共通感染症)、多頭飼育の場合は特に他の動物へも感染が起こりやすくなります。犬や猫の腸管に常在していますが、保菌率はそれほど高くない(1%前後)とされています。また、免疫力の低い子犬や子猫、ストレスの多い環境下や免疫力が低下しているときに発症することがあります。 -

マカダミアナッツ中毒
ナッツ類は脂肪分も多く、消化されにくい食べ物ですので、食べると下痢などの消化器症状を現したりすることがあります。特に犬にとって、マカダミアナッツは中毒を引き起こします。 マカダミアナッツは、他のナッツ類と一緒かそのままの形で売られている製品やチョコレート(※チョコレートはチョコレート中毒を引き起こします)、クッキー、ケーキなどさまざまな食品に使われていますので、その様な製品が犬の周囲に無いか注意しましょう。 -

リンパ腫(犬編)
リンパ腫(りんぱしゅ)は、悪性リンパ腫(あくせいりんぱしゅ):リンパ肉腫(りんぱにくしゅ)などとも呼ばれ、体の免疫を担うリンパ球が癌化してしまう病気で、血液中にある白血球の一つであるリンパ球が癌化する造血器系の癌の一種です。犬の腫瘍中では比較的発生率が高く、腫瘍全体の7~24%を占めています。推定年間発生率は10万犬当たり、20〜100犬程度と報告されています。[4] 悪性リンパ腫は、解剖学的な位置から「多中心型」「縦壁型」「消化器型」「皮膚型」などに区分されます。これらのうち、犬の場合は体のリンパ節に腫れがみられる「多中心型リンパ腫」が大半(リンパ腫全体の 80 %以上)です。6歳以上の中高齢犬に多くみられますが、若齢でも発症します。性別差はありません。 犬種別では、ゴールデン・レトリーバー、ラブラドール・レトリーバー、ボクサー、ロットワイラー、バッセト・ハウンド、セント・バーナード、ブルマスティフ、ブルドック、ジャーマンシェパード、バーニーズ・マウンテンドック、スコットランド・テリアなどがリンパ腫になりやすいと言われていますが、データは国により多少異なります。 逆に発生リスクの低い犬種はダックスフンド(日本では例外)、ポメラニアン、チワワ、ミニチュア・プードル、トイ・プードル、チャウチャウ、ヨークシャー・テリアが挙げられています。 -

胆嚢粘液嚢腫
胆嚢とは、肝臓にくっついている袋状の構造物で、肝臓で作った脂肪の消化に重要な役割を果たす胆汁を蓄えて、濃縮しています。食事をするとこの胆嚢が収縮し、収縮に伴い、胆汁は総胆管を通って十二指腸に放出されます。 胆嚢粘液嚢腫(たんのうねんえきのうしゅ)とは、何らかの原因で胆嚢の中にゼリー状の粘液物質(ムチンという糖タンパク質)が貯留した状態をいいます。また、胆泥症から胆嚢粘液嚢腫になる事もあります。粘液物質が増加すると胆汁の分泌を障害するために様々な消化器症状を引き起こし、状態が進むと、黄疸や胆嚢破裂に伴う腹膜炎などの重篤な合併症を引き起こします。 中〜高齢の犬に多く見られ、猫では稀な病気です。 -

元気消失
元気消失(げんきしょうしつ)は元気喪失(げんきそうしつ)、元気沈退(げんきちんたい)などとも言われ、病気の名前ではなく症状の名前です。動物病院を受診する原因の中でも最も多いもののうちの一つではないでしょうか? 元気がなくなった、いつもと比べてなんとなく動きが鈍いなどは病気の症状かもしれないと多くのペットオーナーが思われることでしょう。 -

バベシア症
バベシア症は、バベシアと呼ばれる顕微鏡でしか見えない小さな原虫という病原体が、血液中の赤血球に寄生することによって溶血性貧血などいろいろな症状をひき起こす病気です。治療が遅れると死に至ります。病原体であるバベシアはマダニの体内に潜んでいて、マダニの吸血とともに犬に感染します。日本国内では病原性の比較的弱いバベシア症(Babesia gibsoni)が関西以西の西日本・四国・九州・沖縄地方に多く発生していますが、近年では東日本以北での犬の感染例も報告されています。壱岐島内でも複数バベシア症の発生(壱岐全島地域)を確認しています。